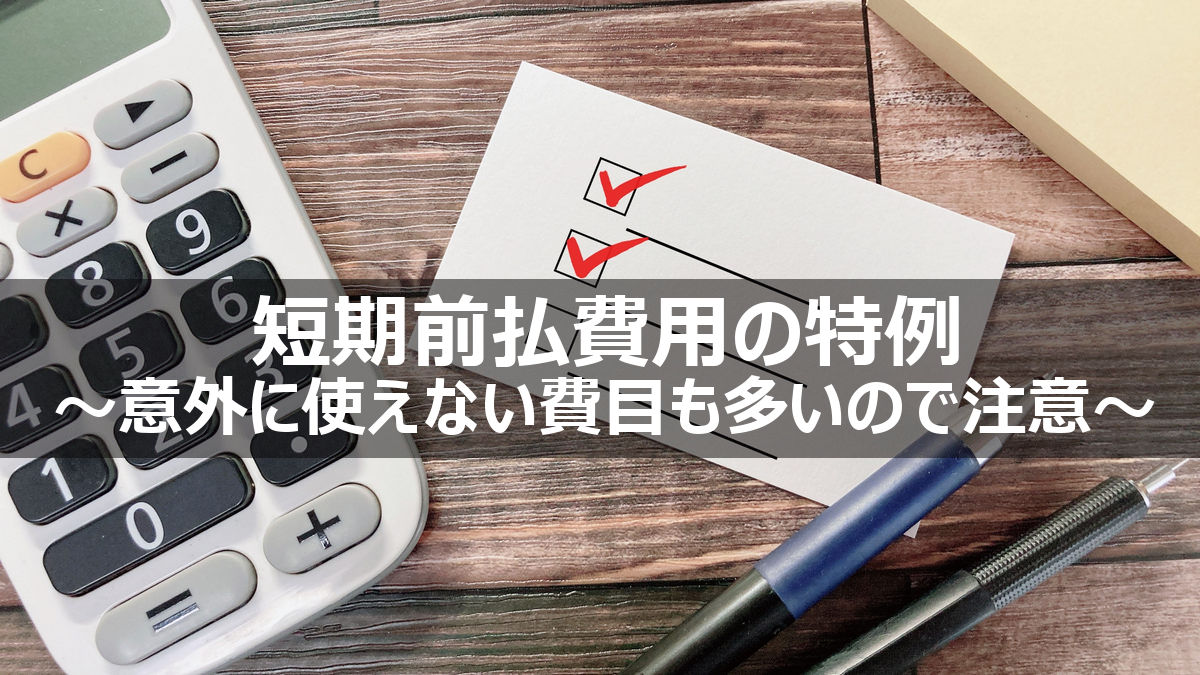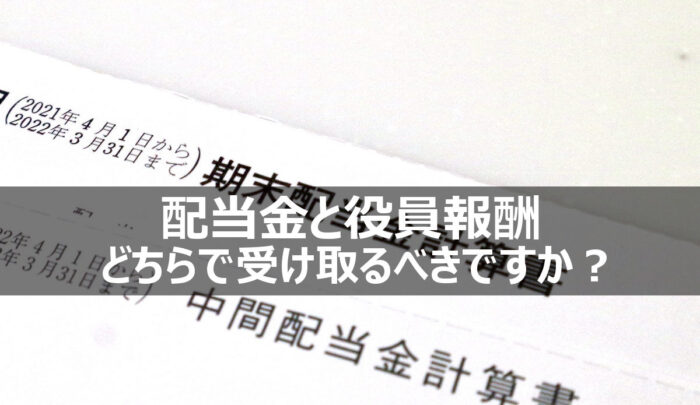節税対策の1つとして短期前払費用がよく挙げられますが、どういったものか知っていますか?また、本当に節税効果は有るのでしょうか?
ここでは
- 短期前払費用はどんな性質をもっているのか?
- 節税効果の有無
- 短期前払費用として損金算入出来る項目・出来ない項目
などについて見ていきましょう。
しっかりと理解せずに活用しようとすると、税務調査で思わぬ否認に合う事も有るので注意が必要ですよ!
そもそも前払費用とは?
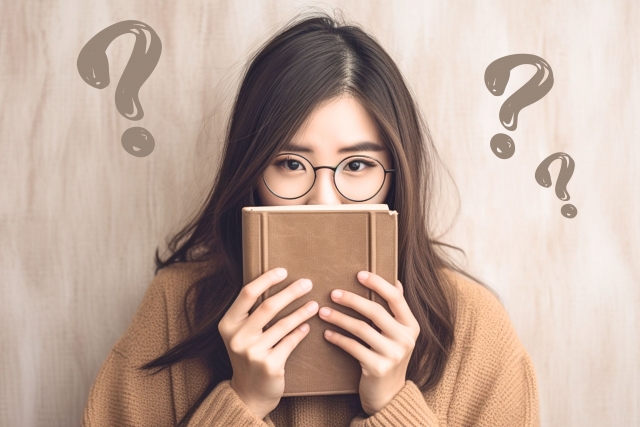
短期前払費用を見る前に、まずは「前払費用」について簡単に見ておきましょう。
前払費用とは、読んで字の如く「前払いをした費用」という意味です。費用という名前が付いていますが資産(経過勘定項目 ※)ですよ。
通常、サービス(役務の提供)を受けた場合、受けたサービスに応じて料金を支払いますよね。しかし、中には事業年度終了時点でまだサービスを受けていないにも関わらず、支払を先にしているというケースも有ります。
そのような場合、まだサービスを受けていない分については前払費用として資産計上し、支払った事業年度の損金には算入しないのです。
そして損金算入するのは、実際にサービスを受けた翌期となります。
【原則】前払費用の仕訳や消費税

前払費用を計上する際の仕訳を見てみましょう。
例えば、3月決算の会社が10月に1年分の事務所家賃として200万円を支払った場合、支払時は以下の様な仕訳となります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 2,000,000 | 現預金 | 2,000,000 |
そして、決算仕訳で未経過の半年分について前払費用に振り替えます。振り替える金額は、1,000,000円(=2,000,000円÷12ヶ月×6ヶ月)です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前払費用 | 1,000,000 | 現預金 | 1,000,000 |
翌期の4月になると前払費用を損金として振り替えます。なお、月次損益を厳密に把握したい場合は、前払費用を1ヶ月分ずつ振り替える様にしましょう。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 1,000,000 | 前払費用 | 1,000,000 |
ちなみに、消費税の課税仕入は、原則として資産の引き渡しやサービスの提供が有った時点で認識する(参照元:国税庁「タックスアンサー 前受金や前払金などがあるとき」)ので、上の例では1年分の家賃を支払った事業年度に6ヶ月分、翌期に残りの6ヶ月分の課税仕入を処理する事になりますね。
短期前払費用は損金算入可能!

上述の通り、原則として前払費用は資産計上し、実際にサービスを受けたときに損金計上する事になります。
しかし、例外的に、継続して同じ処理をする事を条件に、支払から1年以内にサービスを受けるものについては支払った時点で損金算入する事が出来るのです(参照元:国税庁「法人税法基本通達2-2-14」)。
これを条件として分かりやすく箇条書きにすると、以下の通りとなります。
- 支払は契約に基づくものである
- 継続的に役務の提供(等質等量のサービス)を受ける契約である
- 1年以内に提供を受ける役務の対価を前払いしている
- 継続して支払時に損金算入している
- 収益と対応させるべき費用(直接的な見合関係にある費用)ではない
上で紹介した1年分の家賃を支払った例では、支払った時点で全額損金にして決算時点では何ら処理を行いません。つまり、以下の仕訳だけでOKという事ですね。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 地代家賃 | 2,000,000 | 現預金 | 2,000,000 |
短期前払費用と消費税の関係
前払費用として処理した場合、実際に役務の提供を受けた時点で課税仕入として処理をします。
一方で、短期前払費用として、1年以内の前払分を損金計上した場合、消費税の課税仕入は支出した日の属する事業年度に行ったものとして処理をします(参照元:国税庁「消費税法基本通達11-3-8」)。
つまり、短期前払費用は実際に役務の提供を受けた期に課税仕入とするのではなく、支払をした期に課税仕入として処理をするという事ですね。
短期前払費用を活用しても節税効果は得られない?

短期前払費用は、継続的な役務提供契約によって毎期継続して同じ金額を支払う場合に「トータルで見ると同じ結果になるので、わざわざ期間損益の対応を考えて処理をしなくても良いですよ」、という趣旨で認められたものです。
家賃で考えてみると、月払いで払おうが年払いで払おうが1年間で損金算入出来るのは12ヶ月分です。従って、短期前払費用として処理をしたからといって、トータルで考えると税金の負担が減る訳では有りません。
なお、初めて支払をする年限定ですが、例えば3月決算の会社が10月に保険の契約して1年分を前払いすると、月払いするよりも半年分多く損金算入される事になるので、その期に限って言えば節税効果が有ります。
しかし、年払いをするという事はそれだけお金が手元から出て行くという事です。契約初年度の税金を減らす為だけにわざわざ年払いして当座の資金を失うよりは、毎月コツコツと払った方が懸命と言えるでしょう。
なお、過去には家賃や広告宣伝費、旅費交通費など総額2億円超を短期前払費用として処理し、税務署に否認されたケースも有ります(東京地方裁判所平成14年(行ウ)第338号法人税更正処分等取消請求事件(棄却)(控訴)平成17年1月13日判決 [税務訴訟資料 第255号-10(順号9891)])。
2億円の短期前払費用は、さすがに重要性が無いとは言えないですよね。過度な節税対策は税務署に目を付けられる可能性が有るので控えめに。
短期前払費用として処理する際の注意点

短期前払費用として処理する際には、いくつか注意点が有ります。これを守らないと、支払った時に一括で損金処理が出来ないのでしっかりと理解しておきましょう。
・「利益が出た時だけ前払い」は×
・「月払い契約なのに勝手に年払い」は×
・「支出時から1年を超える期間の支払」は×
・決算日までに支出をしていないと×
「利益が出た時だけ前払い」は×
まず、短期前払費用として処理する為には、毎期継続して同じ処理をする必要が有ります。「今期は利益が出たから前払いしてたくさん損金計上しよう」といった融通は効きません。
一度決めたら、その処理方法を続ける様にしましょうね。
但し、未来永劫同じ処理をしなければならない、という訳ではないです。最低3〜5年程度継続して適用していれば変更しても問題無いでしょう。
「月払い契約なのに勝手に年払い」は×
短期前払費用として処理するには、契約に基づいて支払をする必要が有ります。契約上は月払いとなっているのに、たくさん損金にしたいからといって勝手に1年分を支払うのは駄目です。
短期前払費用として処理しようと考えているのであれば、必ず契約の相手方に支払方法の変更を申し出る様にしましょう。
「支出時から1年を超える期間の支払」は×
短期前払費用として損金算入出来るのは、「支出時から1年以内」の期間分です。「決算時から1年以内」ではないので注意しましょう。
例えば、3月決算の会社が12月に4月から翌3月分までの支払をした場合、決算時点で考えると1年分ですが支払時点で考えると16月先の分までを支払っている事になります。
この様なケースでは短期前払費用の適用は有りません。
なお、質疑応答事例では以下の事例が適用出来ないものとして紹介されています。
事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。
短期前払費用の取扱いについて|国税庁 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
決算日までに支出をしていないと×
短期前払費用として処理が出来るのは、決算日までに実際に支払った分のみです。従って、未払だったものを短期前払費用として損金計上する事は出来ません。
決算期末日に口座引落しをする様にしていると、銀行の営業日次第で翌期の支払になってしまう事も有ります。支払が翌期になると短期前払費用として処理出来ないので、確実に当期中に支払を済ませる様にしましょう。
短期前払費用として損金算入出来る項目・出来ない項目

短期前払費用として、支払ったときに一括で損金算入する事が認められているからといって、何でもかんでもまとめ払いをすれば良いという訳では有りません。
短期前払費用として損金算入出来る項目と出来ない項目とが有るので、しっかりと理解をしておきましょう。なお、短期前払費用として処理出来ない場合は、原則通り時の経過に応じて損金算入する事になります。
損金算入出来る項目
まずは、短期前払費用として損金算入出来る項目です。
主なものに以下の様なものがあります。
- 地代家賃
- 保険料
- リース料
- 保守料
それぞれ規定を見ながら詳しく見ていきましょう。
地代家賃の前払い
家賃は継続的に役務提供を受ける契約なので、契約に従って前払いをするのであれば短期前払費用として処理する事が可能です。
なお、以下の様に国税庁の質疑応答事例「短期前払費用の取扱いについて」で、短期前払費用として扱う事の出来る地代家賃の例が紹介されています。
事例1:期間40年の土地賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の地代月額1,000,000円を支払う。
事例2:期間20年の土地賃借に係る賃料について、毎年、地代年額(4月から翌年3月)241,620円を3月末に前払により支払う。
事例3:期間2年(延長可能)のオフィスビルフロアの賃借に係る賃料について、毎月月末に翌月分の家賃月額611,417円を支払う。
事例1・3は毎月末に翌月分の地代家賃を支払う、というよく有る契約形態ですね。この場合は問題無く地代家賃として処理出来ます。また、事例2のように決算期末に1年分の地代を支払って損金に算入する事も可能です。
保険料の前払い
保険料は毎期更新して支払し続けるものであれば、短期前払費用として処理する事が出来ます。
なお、自賠責保険料は通常2〜3年の期間で加入しますが、これについては実務上支払時い全額損金処理しても問題無い、とされています。
これは、「自賠責保険は加入が義務であり、租税公課としての性格がある」「加入期間が最長3年で、金額的に大きく無い」事などが理由です。もちろん、前払費用として厳密に処理する方が好ましいですが、処理が煩雑になるのでよほどの理由がない限りは支払時に全額損金とした方が良いでしょう。
リース料の前払い
リース料についても契約上前払いをする事になっているのであれば、短期前払費用として扱う事が可能です。
質疑応答事例では、以下の様な例が短期前払費用として紹介されています。
事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う。
但し、リースについては注意点が有ります。それは、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引(いわゆる所有権移転外リース取引)には適用出来ないという事です。
所有権移転外リース取引は、減価償却の対象(リース期間定額法)となるので前払いをしたとしても短期前払費用の適用が有りません。
中小企業の場合、会計処理の負担を考慮して一定の条件を満たす所有権移転外リース取引について、リース料の支払時に損金処理する事が認められています。しかし、それはあくまでもリース取引の例外処理なので、それに対して短期前払費用の適用をする事は出来ません。
保守料の前払い
事業をしていると、パソコンやコピー機、エレベーターなどで様々な保守契約を結ぶ事が有りますよね。保守契約に基づいて支払う保守料は、短期前払費用の対象となるのでしょうか?
この点、保守契約によって提供される役務の内容は、たとえ毎月の料金が同じだったとしても等質等量とはいい難いですよね。
しかし、国税庁が「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」のⅦで解説に使用している事例を見てみると、保守契約について短期前払費用が適用出来る前提で解説をしています。
このQ&A自体は、消費税が5%から8%に引き上げされた時の解説なので、短期前払費用として処理する事を認めるものでは有りません。しかし、適用出来るケースしか事例として使用しないでしょうから、保守契約については短期前払費用として処理出来ると考えて良いでしょうね。
万が一税務調査で指摘されたら、このQ&Aを見せてみるのも良いでしょう。
損金算入出来ない項目
続いて損金算入できない項目の事例を見ていきます。解説するのは以下の5項目です。
- 転貸物件の前払家賃
- 顧問料
- 雑誌の購読料
- 広告宣伝費
- 社員旅行費用
借りているマンションやビルを転貸している場合の前払家賃
自社で使うビル等の賃料を前払いする分に関しては、上述した様に短期前払費用の適用が有ります。
しかし、賃借物件を他に転貸したり社宅として従業員等に住まわせて賃貸料収入を得ているような場合、収益(賃貸料収入)と費用(地代家賃)とを期間対応させる必要が有るので、家賃を前払いしても全額を支払時の損金とする事は出来ません。
顧問料や雑誌の購読料の前払い
税理士の顧問料や雑誌の年間購読料といったものは、例え1年分を前払いしたとしても短期前払費用として処理する事は出来ません。
これは、サービスの中身が等質等量ではないからです。家賃や保険料などは毎月同じ質や料のサービスを受ける事が出来ますが、顧問料や雑誌の購読料などはサービスの内容や料が毎月同じとは言えません。
従って、短期前払費用の適用対象外です。
期間限定の広告宣伝費
期間限定で雑誌やテレビCMに広告を掲載する為の広告宣伝費は、継続的なサービスの提供とは言えないですし、時の経過に応じて費用化する様な性質ではないです。
従って、広告料を前払いしたとしても短期前払費用として損金に算入する事は出来ません。
社員(慰安)旅行の前払い
例えば、3月決算の会社が翌期の6月に行われる社員旅行にかかる旅費を3月中に支払ったとしても、短期前払費用として損金処理する事は出来ません。
これは、社員旅行が継続的に役務の提供を受けるものではなく、単発に行われるものだからです。
受取側の処理は?
役務の提供を受ける側が前払をして短期前払費用の取扱をする場合、対価を受け取る側の処理はどうなるのでしょうか?
この点、受取側は支払側の処理がどうであろうと当事業年度に収益とすべき金額のみを計上します。消費税についても同様です。
そもそも、前払いをしたからといって支払者が支払時に全額損金とするか原則通り前払費用として処理するかは、受取側には関係の無い話ですからね。
短期前払費用は所得税でも適用有り!
ここでは法人を前提に書いていますが、個人事業主(所得税)の場合も短期前払費用の適用が有ります(参照元:国税庁「所得税基本通達37-30の2」)。
従って、上で紹介した要件を満たす限りは、個人事業主の事業所得を計算する上で必要経費に算入する事が可能です。
まとめ
契約内容や支払方法によっては、短期前払費用として支払時に全額損金算入出来る事が分かりましたね。
但し、契約初年度は節税効果が有りますが、トータルで考えると税負担は基本的に変わりません。前払いにするかどうかは、税負担よりも資金繰りを中心に考えた方が良いでしょうね。